「今日あったけぇな」。この言葉を耳にしたとき、あなたは何を思い浮かべるでしょうか?特別な状況や場所を特定しなければ、一般的な解釈としては、特別に暑い日を表す表現として捉えられることでしょう。例えば、国の中心部、東京都内である場合、ある人がこの表現を使うとき、おそらくそれは気温が30℃を超え、汗ばむ肌や焼けつくようなアスファルト、差し込む強烈な日差しといった、真夏日を想起させるでしょう。しかし、この言葉が口にされる状況は、場所によって大きく変わることもあります。たとえば、日本の北の果て、北海道網走市の住民がこの言葉を発したとき、その基準は私たちの想像を大いに超えるかもしれません。厳しい冬の寒さに慣れた彼らにとって、「あったけぇ」とは、たとえば冬季でも気温が氷点下にならない日を指して使われるかもしれないのです。そのため、同じ「あったけぇ」でも、それが口にされる環境や状況により、その意味合いは驚くほど異なるのです。
私の仕事は地域密着型の記者であり、同時にトップブロガーでもあります。多くの人々が、単なる情報提供者として私を見るかもしれません。しかし、私は自分自身をそうは見ていません。私のライフワークは、微細な違いを追求し、それが生まれる土地の独特な雰囲気を感じ取ることです。毎日、その探求の求道者として時間を過ごすことで、地域の人々が日々使う言葉の奥深さに気づくことができます。それらの言葉には、その地域の特性や文化が深く根ざしていることを感じます。
それは、その地域独自の気候や地理的な特性が生み出す言葉の微妙なニュアンスを読み解くことから始まります。更にその背後に存在する風土、人々の営みや生活様式を探求することで、私はその地域の真髄を理解しようと努力しています。地域の言葉に隠された緻密な表現や独特の表情、それらが表す地域の感情や個性を垣間見ることは、私にとって無比の喜びとなります。
私の活動が地域社会に対してどのような影響を与えているかははっきりとは分かりませんが、少なくとも私自身に影響を与え、成長させてくれることは間違いありません。この探求の旅は、私に日々新たな驚きや発見をもたらし、さらに深く進むことを促してくれます。それが私が、日々を過ごしながら追い求めている微妙な違いの探求なのです。
冬の季節が訪れると、我々の心に浮かぶのは、白銀に輝く風景、凍えるような冷たさ、そして、それを凌ぐ温かさです。そんな中、今回は特に寒さで知られる北海道網走市での冬の体験を通して、どの程度の気温が地元民にとって「あったけぇ」と感じられるのか、そして、それが全国的な感覚とどう違うのか、という観点から探ります。北海道といえば、日本列島最北の大地であり、冬季の厳しい寒さは我々日本人にはよく知られています。特に網走市はその中でも深い冬を経験する地域として知られています。しかし、その一方で、独特の冬景色、雪をまとう自然、美しい氷の彫刻のような流氷など、その極寒の中にも見るべき価値があります。そんな網走市の冬景色の中へ一緒に足を踏み入れてみましょう。地元民たちが寒さをどのように感じ、どのように対処しているのか、そして、全国的な感覚とどのようにズレているのかを比較し、理解を深めることで、きっと新たな視点から冬の魅力を発見することができるでしょう。
北海道網走市の冬
日本最北の都市、網走市は非常に過酷な冬の季節を迎えます。この地の冬の厳しさは、文字通りの意味で身を持って体感なければ理解できない程です。ガラスを覆いつくす結晶の花、雪の風景が広がる街並みは美しいですが、その一方で平均気温はマイナス10℃以下にまで下がり、最低気温ではなんとマイナス30℃を下回ることもあります。その驚異的な寒さは、人々の身体に深く染み込み、その強烈さを物語ります。しかし、網走市の住民たちはこの厳しい寒さにもめげず、生活の一部として受け入れています。そんな彼らが「あったけぇ」と口にするのは、普通の地域であれば厳冬と呼べる気温、つまり、気温が0℃に近づく、あるいはそれを上回った時なのです。これは、極寒の地網走の冬を生き抜くための彼らなりの感覚の転換かもしれません。0℃が基準であり、それが彼らの「あったけぇ」という基準です。まさに網走市の冬は、その人間性を試す試練の場であり、生活の知恵と工夫、そして人々の強靭な精神力が試される季節なのです。

これは、昔から厳しい寒さと日々向き合いながら生活を営んできた市民たちの感覚が如実に反映されています。寒さは彼らが日々抱える厳しい現実であり、その環境が育んだ独特の感覚は、我々の思考や価値観に大きな影響を与えています。氷点下という厳しい寒さから、ようやく0℃まで上昇したとしても、彼らにとってはそれが「暖かさ」を意味するのです。このあたりには、彼らが体験する日常生活の中での当たり前の感覚や経験が、彼らの認識を形成し、そしてその認識が全国的な感覚とは大きく異なる基準を生み出しているという事実が見て取れます。このように、その土地の気候や自然環境が人々の感覚を左右し、その地域特有の視点や価値観を生み出しているのでしょう。その土地、その人々の”暖かさ”の基準は、他の場所では理解し難いかもしれませんが、それがブレない理由は、彼らがその地で生活する上での必然性に他ならないのです。
全国基準とのズレ
都市部、特に繁華街に生息する我々にとって、ふと自分が「あったけぇ」と感じる瞬間が訪れる温度の基準は、決して低いものではないことに気付かされます。それは我々が、一年を通じて温度変化の激しい環境で生活を営むという生活スタイルに馴染んでいるからでしょう。首都圏などの大都市では、夏季の日中の平均気温が25度を軽く超え、日によっては30度を越えるような猛暑日が続くこともしばしばです。このような夏の日々を体感しながら生活することで、我々が「あったけぇ」と思う感覚の基準が自然と上昇していくのかもしれません。その基準は、大体、外気温が20度を超えたあたりから始まるようです。とはいえ、この温度基準はあくまで我々都市部に生息する者たちの感覚であり、地域や気候条件によって大きく異なるでしょう。例えば、北海道の網走市など、冬季に厳しい寒さが訪れる地域の住民にとっての「あったけぇ」は、我々都市部住民が感じるそれとは、かなり異なるものになることでしょう。彼らはおそらく、我々が寒いと感じるような温度でも「あったけぇ」と感じてしまうのかもしれません。こう考えると、我々が感じる温度感覚は、我々が生きている環境に大きく影響されていると感じさせられます。

しかし、この小さな「ズレ」こそが、私たち日本の多様性と地域固有の文化を示すものなのです。全国一律の基準や感覚に縛られず、各地域が持つ独自の価値観や基準が存在するからこそ、その地域の風土や生活感がより豊かに、より深く感じられるのではないでしょうか。この地方色が強く表現される瞬間こそが、我々がその土地の魅力や特性を理解し、共有する一助となるのです。そこには、季節の移ろいや地域の暮らしを映し出す料理、伝統的な祭り、方言といった風土を形成する多くの要素が組み込まれています。これらは規格化された価値観からは見えない、その土地ならではの文化や生活の豊かさを私たちに示してくれます。全国的な感覚とは異なる基準が存在することによって、その地域の風土や生活感が一層引き立ち、私たちの心を豊かにするのです。
わたしの体験
私が初めて北の大地、網走市を訪れた時、その厳しい寒さが肌に突き刺さるのを、はっきりと覚えています。冷たい空気が鼻を突き刺し、息を吹き出すと白い霧となって舞っていました。無情にも吹きつける風が、思い切り自分の存在を主張するかのように感じられました。しかしその一方で、地元の人々が「あったけぇ」と口にする日の、その暖かさに触れた瞬間、私の心は温かく包まれ、どこか安堵の感覚に浸りました。それは、十分ではないかもしれないけれど、体が心地よく感じてしまうような0℃の「暖かさ」だったのです。体が小さく震え、寒さにうなされながらも、その「暖かさ」に触れることで、彼らが厳冬の中でどのように生活しているのか、その生活感が僅かながらも私の心に伝わってきました。それは彼らが自然とともに生きている、厳しさの中にもぬくもりを感じる生活の一端を、私に見せてくれたかのようでした。
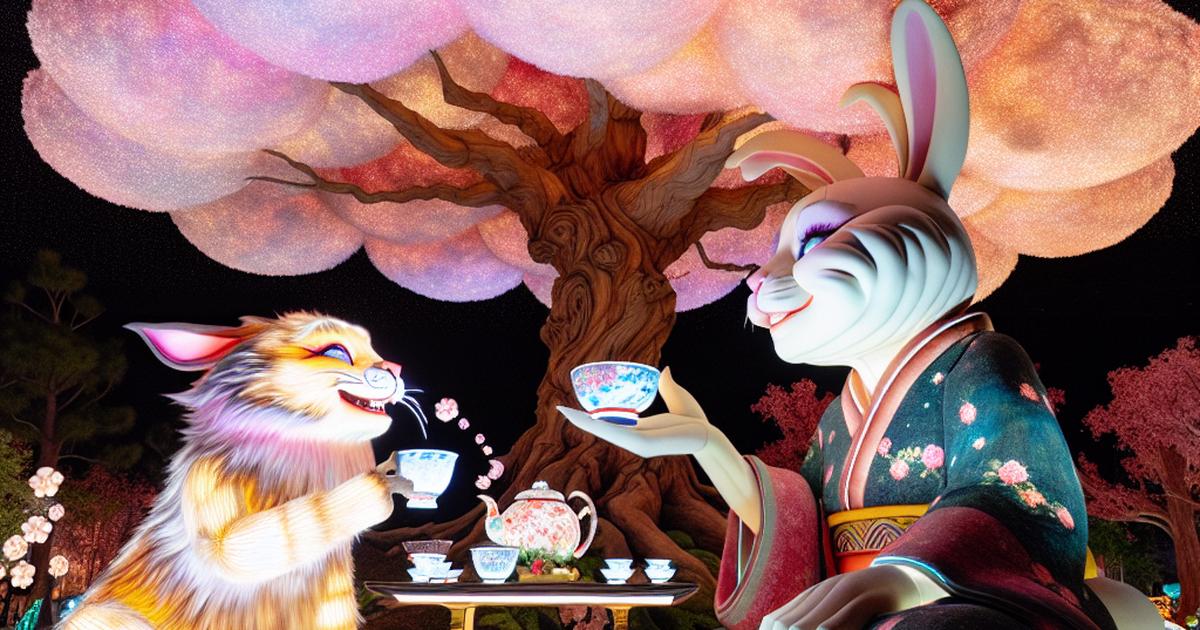
そんな網走市民の感じ方を知った私は、自分の「あったけぇ」の感じ方が少し変わったことに気付きました。もちろん、それは単純な物理的な温度の増減だけを指すのではありません。それは、心地よい暖かさを感じていた私が、ただ「あったけぇ」と感じるだけでなく、新たな視点からその「暖かさ」を評価するようになった、ということです。これまで私が感じていた「暖かさ」は、外からの刺激に反応する体の感覚だけでした。しかし、網走市民の基準を知ることで、私は自分自身が「暖かさ」を感じるだけでなく、その「暖かさ」がどのように働き、どのように私自身を含む人々に影響を及ぼしているかを考えるようになりました。この新たな視点は、私が今までに感じてきた「あったけぇ」の感覚を深め、その一方で、新たな「暖かさ」の概念を生み出すことにもなりました。この新たな「暖かさ」の感じ方は、単に感覚的なものでなく、理解と認識に基づくもので、私自身の成長ともいえるでしょう。
まとめ
「あったけぇ」の感覚が、地域によってこうも大きく変わるという事実に、私たちは驚きを覚えることでしょう。私たちが日々感じている「暖かさ」が、他の地域の人々にとっては全く異なる体験であることは、常識を覆すような出来事です。しかし、その違いこそが、一つ一つの地域が持つ独自の風土や感性、生活感を引き立て、地域色を鮮やかに彩っています。北の大地が育んだ厳しい寒さを乗り越える温もり、南国特有の日差しに包まれる柔らかな暖かさ、それぞれが地域の人々の生活の一部となり、その地を愛する理由となっています。私たちは、そうした地域性を大切にし、理解し合うことで、多様な「暖かさ」を感じることができます。それぞれの地域が持つ独特の暖かさを尊重し、体験することで、私たちの心もまた暖かくなるのではないでしょうか。地域の違いを受け入れ、理解することで、私たちはより広い世界を知ることができますし、その多様性は私たちの人生を豊かに彩ってくれます。

今後とも私の旅は続きます。それは多様で繊細な日本の風土を、その微細な違いごとに愉しみ、究めていくたぐいの旅です。地域ごとに異なる風景、土地の人々の暮らしや言葉、そして季節ごとの移ろいゆく色彩…。そんな各地の個性や魅力をじっくりと味わいつつ、私自身が感じたその全てを皆さまにお伝えしていく、そういう旅です。その中で特に印象に残っているのが、東北地方の冬。織りなす美しい雪景色と、温かい人々の心。震える寒さと同時に、「あったけぇ」と感じられる地元の人々の温かさ。全国各地に散らばる、そんな「あったけぇ」を見つけては一緒に感じてみませんか?私たちの日本には、まだまだ知らない魅力が沢山眠っています。私がそれを見つけては、皆さまにお届けする。そんな役割を全うすることが、今の私にできる最善の形だと思います。どうぞ、これからも私の旅を見守り続けていただけますと幸いです。








